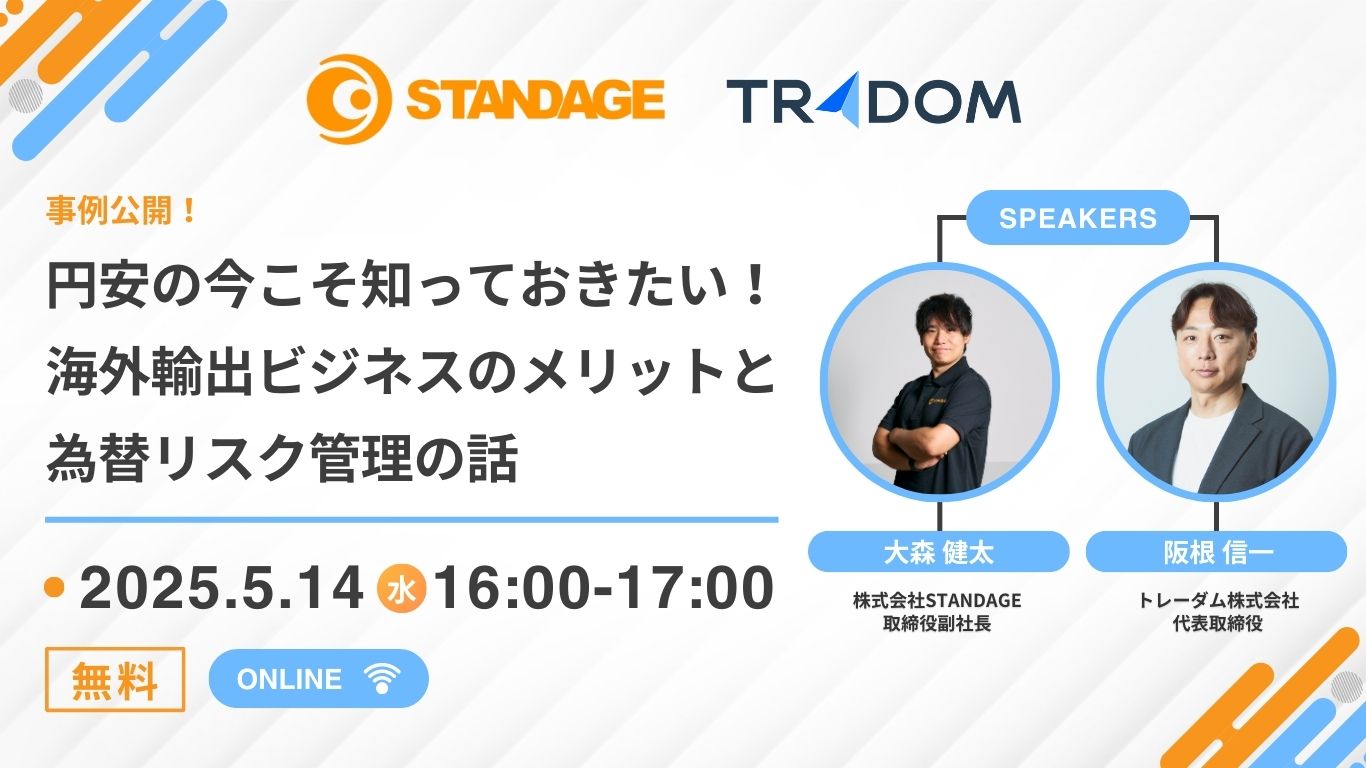―Executive Summary―
- ドル円の変動幅は4月21日週に4.14円と、その前の週の2.47円から拡大した。週足では、4週ぶりに反発。前週比では1.51円の上昇となった。年初来リターンは8.7%安と、年初来で最大だった前週からマイナス幅を縮小した。トランプ大統領によるパウエルFRB議長解任や、米中貿易戦争激化への懸念から売りへ傾き、2024年9月以来の140円割れを迎えたが、その後はトランプ政権から一連の不安を払拭させる発言が飛び出し、一時144円台を回復した。日米財務相会談を控え、ベッセント財務長官が通貨目標を定めないと明言したことも、材料視された。
- ベッセント財務長官は4月23日、講演で「ブレトンウッズ体制の再構築」について説明した。講演で、同氏は「アメリカ・ファースト」は米国の孤立主義を意味するのではなく、国際通貨基金(IMF)や世界銀行のような国際機関における米国のリーダーシップの拡大を意味すると説明。さらに、新自由主義体制で中国が最大の受益者となったような抜け穴を塞ぐ意思を明確化した。あらためて、米国が中国包囲網を構築する上で、国際経済体制の刷新を図る意思を示したと言えよう。そのなかで、日本が通商交渉の「最優先」として位置づけられた意味は大きい。
- 赤沢経済再生相は4月30日から5月2日まで、3日間で訪米し第2回の日米通商協議に向かう。ベッセント氏いわく、日本などとの関税交渉について4月23日に「2段階で進めていく」と方針を表明。日経新聞によれば、①貿易不均衡の是正に向けた「原則的合意」をかわし、②詳細品目へと落とし込んで「実際の貿易文書」の交渉に進む考え――だという。日本側も、まず①農産品や液化天然ガス(LNG)の輸入拡大などに「大枠」で合意、②その上で、実務者などで詳細を詰める――方針。 トランプ氏は4月25日、日本との協議について「我々は合意に非常に近い」と明言したが、米国がスピード勝負を望むなら、一部輸入拡大という大筋合意に目途が立つ期待もある。
- 今週は4月30日に米Q1実質GDP成長率・速報値、米3月PCE価格指数、米4月雇用統計と米重要指標が目白押しだ。足元、一連の指標はやや弱含む公算。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は関税によるインフレ押し上げ効果を踏まえ、利下げに急がない姿勢を貫くが、利下げ転換を示唆するならば、米4月雇用統計の大幅悪化が必要となりそうだ。
- 日銀は4月30日から5月1日に、金融政策決定会合を開く。トランプ関税への不確実性から、今回も据え置きを決定する公算。四半期に一度公表される展望レポートについては、相次いで2025年度の成長と物価の見通しが下方修正されると報じられている。もっとも、日米協議の最中に円安が加速すれば影響を与えかねず、追加利上げの方向性を維持するだけでなく、6月の中間評価を控える国債買い入れ減額ペースの変更について、何らかの示唆を与える可能性にも留意すべきだろう。
- 4月28日週は、29日に米3月雇用動態調査(JOLTS、求人件数など)、米4月消費者信頼感指数、30日は日本3月鉱工業生産、豪Q1と3月のCPI、中国4月製造業PMIと財新製造業PMI、独4月小売売上高、独4月失業率、ユーロ圏と独のQ1GDP成長率・速報値、独4月CPI速報値、米4月ADP全国雇用者数、米Q1雇用コスト指数・速報値を予定する。また、米Q1実質GDP速報値や米3月PCE価格指数などを予定する。5月1日は、米新規失業保険申請件数や米4月ISM製造業景気指数、2日は日本3月失業率や有効求人倍率、ユーロ圏と独の製造業PMI確報値、ユーロ圏4月消費者物価指数(HICP)速報値、米4月雇用統計を予定する。
- その他、4月30日から5月2日にかけ、赤沢経済再生相が訪米し日米協議を行う、また、5月1日は日銀の政策発表と植田総裁の記者会見を予定する。
- ドル円のテクニカルは、弱い地合いが後退。一目均衡表では引き続き三役逆転を形成し、21日線を始め移動平均線は全て下向きだが、一目均衡表の転換線と期間21日のボリンジャー・バンドの-2σのラインを上回ってきた。弱い地合いが後退したため、重要イベントと指標次第だが、戻りを試す余地がありそうだ。
- 商品先物取引委員会(CFTC)が発表した投機筋による円のネット・ポジション動向は、4月22日週時点で17万7,814 枚と、前週の17万1,855枚を超え12週連続でロングなだけでなく、3週連続で過去最大を更新した。米中間の強硬姿勢に緩和の兆しがみられるなか、円ロングは一旦縮小する雲行きと言えよう。一方で、レバレッジ系(ヘッジファンド勢など)による円先物のネット・ポジション動向は、4月22日週時点で1万9,443枚と、前週の1万8,100枚を上回り、2019年9月以来の高水準だった。トランプ1期目の水準まで、円ロングが拡大した格好。日米協議が継続するなか、早々に円ロングが解消されるかは不透明と言えよう。なお、レバレッジ系の円ロングは2008年3月の6万5,771枚で、まだ円ロングの余地を残す。
- 以上を踏まえ、今週の上値は一目均衡表の転換線が近い145.50円、下値は4月23日の安値付近の141.50円と見込む。
1.先週のドル円振り返り=FRB議長解任と米中貿易戦争激化懸念で140円割れも、一時144円台へ戻す
【4月21~25日のドル円レンジ: 139.89~144.03円】
ドル円の変動幅は4月21日週に4.14円と、その前の週の2.47円から拡大した。週足では、4週ぶりに反発。前週比では1.51円の上昇となった。年初来リターンは8.7%安と、年初来で最大だった前週からマイナス幅を縮小した。トランプ大統領によるパウエルFRB議長解任や、米中貿易戦争激化への懸念から売りへ傾き、2024年9月以来の140円割れを迎えたが、その後はトランプ政権から一連の不安を払拭させる発言が飛び出し、一時144円台を回復した。日米財務相会談を控え、ベッセント財務長官が通貨目標を定めないと明言したことも、材料視された。
21日、ドル円は軟調な推移に。ドル円は前週の流れを受け売りが先行し、ハセットNEC委員長がトランプ氏はパウエル議長の解任を検討中と言及したため、東京時間から売りが先行した。欧州市場がイースターマンデーで休場ながら、一時140.47円と2024年9月以来の水準まで下落。もっとも、ブルームバーグが次回会合で日銀は据え置く見通しと報じられるなか、買い戻しの展開。NY時間にはトランプ氏が再びパウエル氏に利下げを要請したものの、反応薄だった。
22日、ドル円は売り先行を経て買い戻し。ドル円は東京序盤に一時141円台を回復も、パウエルFRB議長解任への懸念に加え、日米財務相会談を現地時間の24日に控えるなか、米国が東南アジア経由の中国太陽電池に高関税、最高3,500%を課すと報じられ、140円を割り込んだ。一時139.89円と2024年9月以来の安値をつけたが、NY時間には買い戻し。ベッセント財務長官が状況は持続不可能で、中国との緊張緩和を予想すると発言したため、急速なリスクオフの巻き戻しが入り、ドル円は141.67円まで本日高値を更新した。なお、IMFが世界経済見通しを発表し、2025年の世界経済や米国、先進国、中国などトランプ関税を受け軒並み下方修正したが、影響は限定的だった。
23日、ドル円は乱高下を経て上昇。トランプ氏がパウエル氏を解任するつもりはないと明言したことから、一時143.20円台へ上昇した。ロンドン時間では、日米財務相会談を控え、シティグループが1ドル=120円前後が目標で妥結の見通しを示したことで、売りに反転。もっとも、NY時間は買い戻しが優勢。トランプ政権が米中貿易戦争激化を回避すべく、対中追加関税の大幅引き下げを検討とWSJ紙が報道したため、急速に買い戻しが入った。加えて、ベッセント財務長官が記者団に対し、日本に通貨目標を求めないと発言したため、ドル円は143円台を回復し、一時143.58円と約1週間半ぶりの水準まで切り返した。
24日、ドル円は前日に143円台を回復した流れを受け、調整地合い。日米財務相会談を控え、結果を見極めたいとの見方から模様眺めムードが広がったが、動意に乏しい。クリーブランド連銀総裁が6月利下げの可能性に言及したが、一時142.28円まで本日安値を更新するにとどまった。
25日、ドル円は買い戻しが優勢に。日米財務相会談を経て、加藤財務相が為替目標について議論しなかったと述べたため、安心感から買いが入った。また、日銀・植田和男総裁がG20財務相・中央銀行総裁会議後の会見で成長見通しだけでなく、物価見通しの修正も示唆し、買いにつながった。中国が貿易戦争による経済的損失を理由に、米国からの一部の輸入品を対米関税の対象外とすることを検討しているとの報道も、買いを後押し。ドル円は143.70円台へ上昇した。ロンドン時間では売りに押されたものの、NY時間は買いが再燃。トランプ氏が、日本との合意が近いと発言したためリスクオンを誘い、一時144.03円と約2週間ぶりの水準は戻しつつ、143円後半で週を終えた。
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!