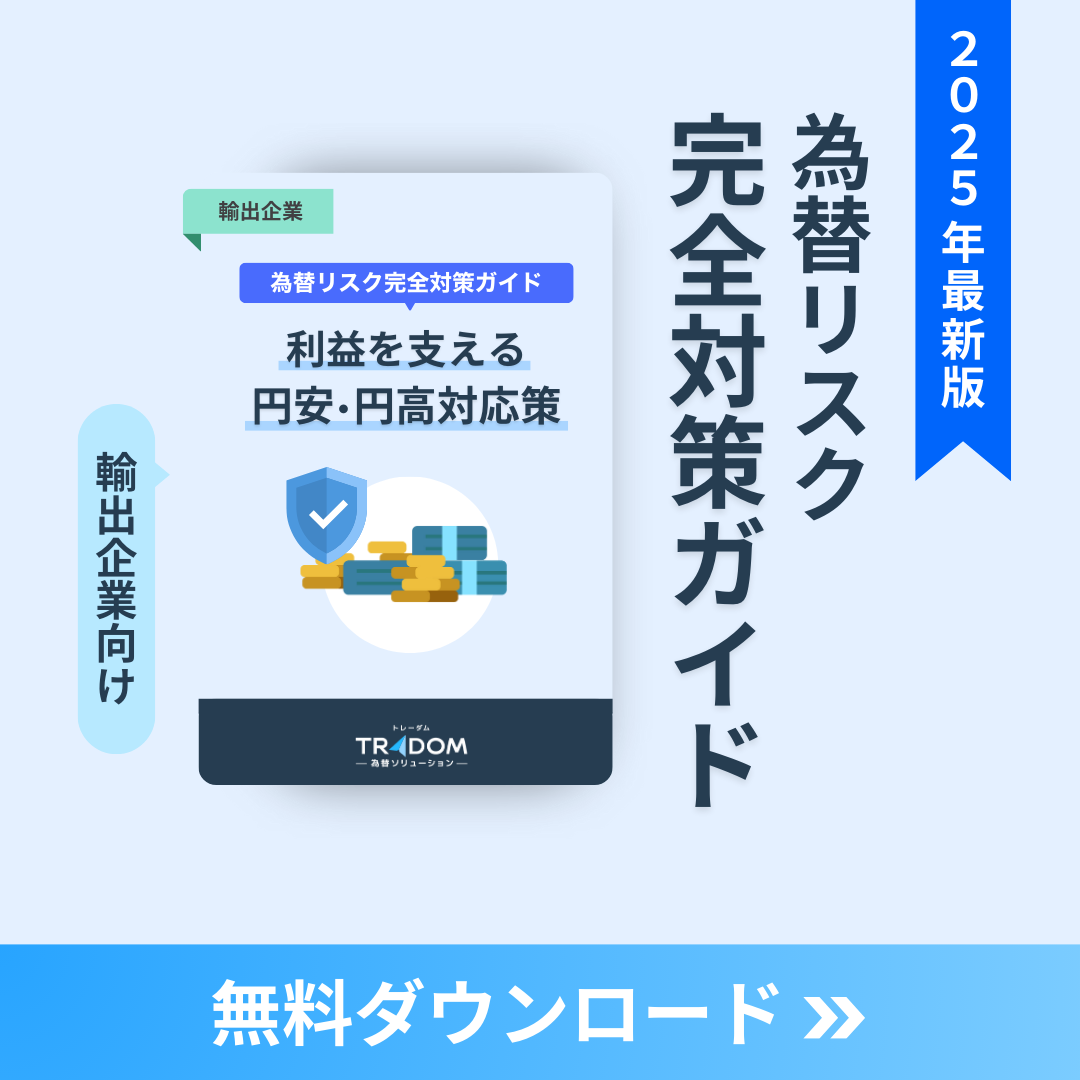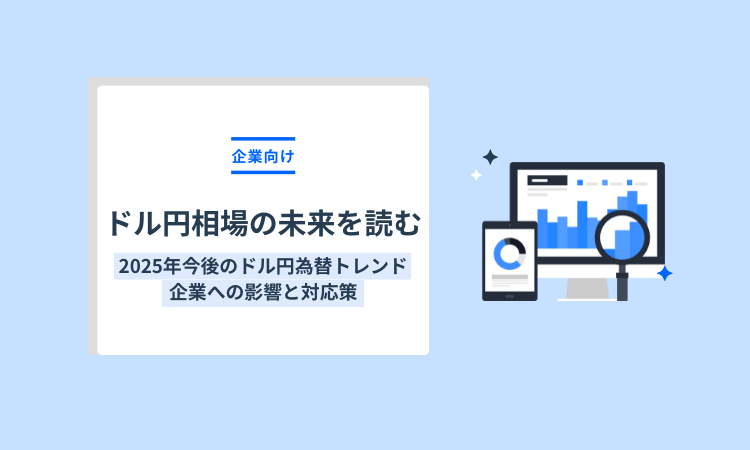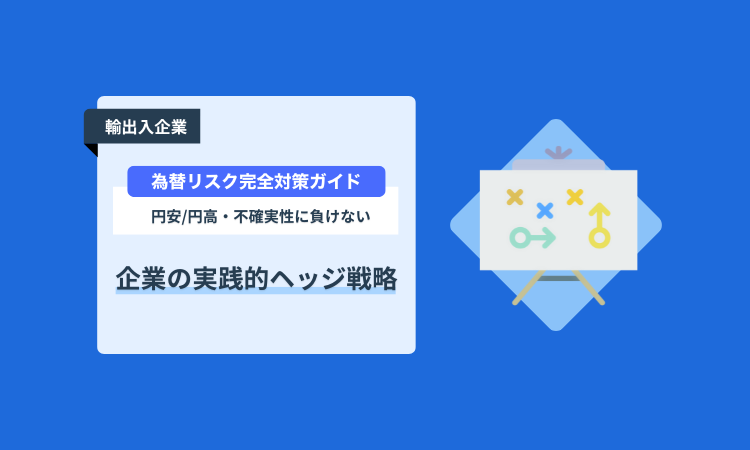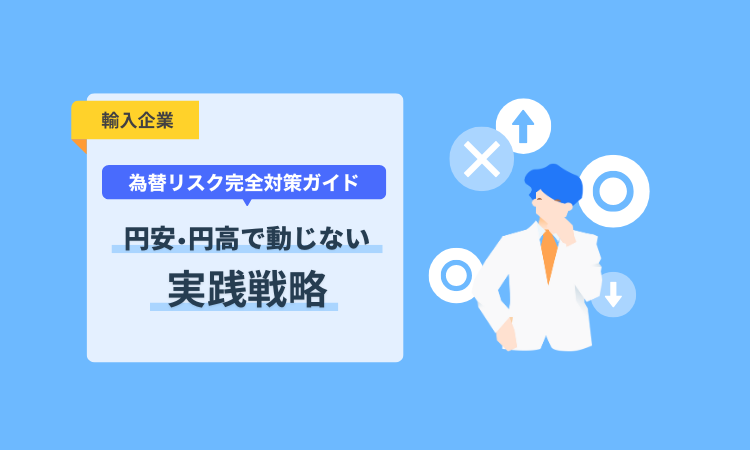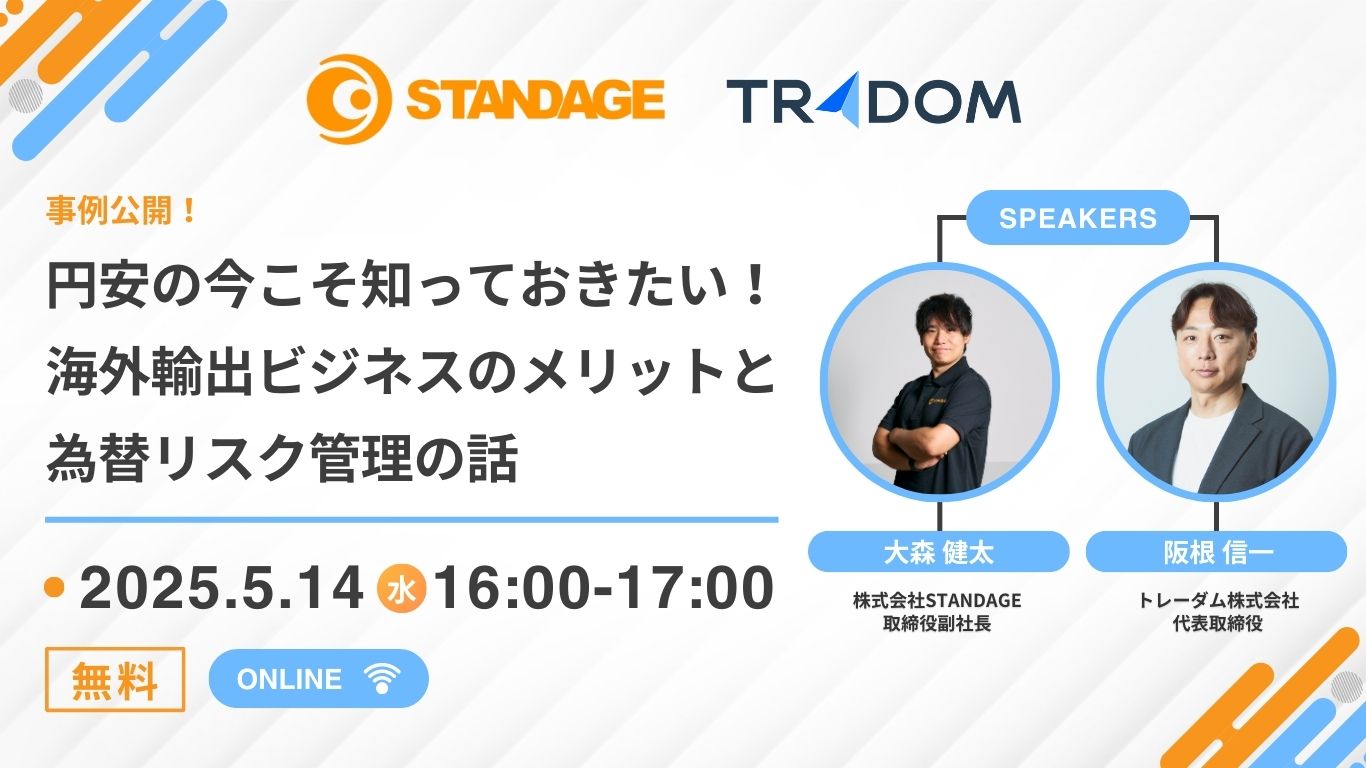目次
為替リスクの基本構造と輸出企業にとっての重要性
日本企業が海外取引を行う際、避けて通れないのが為替リスクです。為替リスクとは、外国為替レートの変動によって企業の収益や費用が変動し、損失が生じる可能性を指します。特に製品を海外に輸出する企業では、売上が外貨建てになるため、為替相場の変動が直接利益に影響します。例えば1ドル=110円で契約した輸出代金も、決済時に円高が進んで1ドル=100円になれば、円換算の売上は減少してしまいます。このように為替レートの変動は利益に直結するため、輸出企業にとって為替リスク管理は経営上極めて重要な課題です。
日本は経済構造的にも輸出への依存度が高く(GDPに占める輸出割合が大きい)、輸出企業の業績は為替に大きく左右されます。円建てではなく外貨建てで売上を計上する場合、その為替エクスポージャー(為替変動にさらされる度合い)は高まり、適切なリスク管理が求められます。為替リスクを放置すると、価格競争力の低下や利益圧迫に繋がり、ひいては企業の競争力や存続にも影響しかねません。そのため、多くの輸出企業では財務担当者や経営者が日々為替相場を注視し、リスクヘッジ策の検討を行っています。為替リスクは短期的な損益だけでなく、中長期的な経営戦略にも関わるため、経営層から現場まで一体となった対応が重要となります。
円高・円安が企業収益に与える影響
為替相場の変動、とりわけ円高・円安は輸出型企業と輸入型企業に対して正反対の影響を及ぼします。一般に「円高ドル安」は輸入企業の業績を向上させる一方で、輸出企業の業績を悪化させ、「円安ドル高」は輸出企業の業績を向上させ、輸入企業の業績を悪化させると考えられます。輸出企業にとって円高(=円の価値上昇)は、外国通貨で得た売上を円に換算したときの金額が目減りする為替差損要因です。一方、円安(=円の価値下落)は、同じ外貨建て売上でも円換算額が増える為替差益要因となります。加えて、為替レートは企業の価格競争力にも影響します。円高局面では日本製品の価格が相対的に割高になるため海外市場での競争力が低下し、販売数量が伸び悩む可能性があります。逆に円安は日本製品の価格競争力を高め、輸出数量の増加につながることもあります。

為替変動が業績に与えるインパクトは企業規模や業種によっても異なります。例えば、大手自動車企業では、対ドルで1円の円安が年間の営業利益を約450億円押し上げると試算されています。逆に言えば1円の円高で同程度の利益が吹き飛ぶ可能性があるということで、為替の変動幅次第では数百億円規模で収益が変動し得るのです。この「1円」の影響は企業によって様々ですが、輸出比率の高い企業ほど大きく、例えば他の自動車メーカーでも1円の円安で数十億円規模の増益要因となるケースが報告されています。輸出企業はこのような為替感応度を把握した上で、為替リスクヘッジを行い業績変動を平準化する努力をしています。一方で、輸入原材料に依存する企業では円安による調達コスト増が利益圧迫につながるため、輸出入両面の取引を持つ企業は円高・円安それぞれのメリット・デメリットを慎重に見極める必要があります。
アメリカ取引と中国取引における為替リスクの違い(実例付き)
日本の輸出企業にとって主要な取引相手であるアメリカと中国では、直面する為替リスクの構造にいくつかの違いがあります。

アメリカ向けの取引: 取引通貨は圧倒的に米ドル建てが主流です。歴史的に見ても、日本企業は米国への輸出取引ではドル建て決済を避けられず、相手先に円建てを受け入れてもらうことは難しいのが現実でした。そのため、日本企業はドルで売上を計上し、為替先物予約(為替予約)や海外生産ネットワークの構築などでリスクを管理してきました。ドル円相場は24時間世界中で取引される流動性の高い通貨ペアである一方、米国の景気動向や金融政策に大きく影響されます。例えば、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測が強まるとドル高・円安が進行しやすく、逆に米国景気悪化や金融不安時には投資家のリスクオフで急激な円高ドル安が起こり得ます。典型的なリスクとして、リーマンショック直後の急速な円高(1ドル=110円台から一時75円台への急騰)や、近年では2022年に急速な円安が進み1ドル=150円前後に達したケースが挙げられます。これらのドル円変動は日本の輸出企業に大きな利益変動をもたらし、為替予約やデリバティブで対応していても想定を超える動きに苦慮する場面がありました。
中国向けの取引: 取引通貨は伝統的に米ドル建てが多いものの、近年は人民元建て決済も増加傾向にあります。実際、日本から中国向け輸出に占める人民元建て比率は、2009年の1.3%から2017年には12.3%へと急拡大しました (国際通貨研究所)。この背景には、中国政府が人民元の国際化を推進し、中国企業側も元建て決済を希望するケースが増えていることがあります。一方で、人民元は対ドルで管理変動相場制を敷いており、為替市場・資本取引に一定の規制が残る通貨です。そのため、元建て取引には独特のリスクがあります。短期的には人民元相場は対ドルで安定的に推移する傾向がありますが、政府方針で突如変動幅が拡大する可能性も否定できません。実例として、2015年には中国人民銀行が人民元を電撃的に切り下げる「人民元ショック」が起き、対ドルでの元安が進行しました。このような政策変更は、元建てで取引する日本企業にも為替差損リスクをもたらします。また、取引がドル建ての場合、中国企業(輸入者)にとってはドル高・人民元安はコスト増要因となり、代金支払い能力に影響する恐れがあります。日本の輸出企業としては、中国向け取引ではドルと人民元のいずれにリスクを負うかを見極めねばなりません。昨今は、人民元建てを採用することで中国市場での競争力を高めつつ、元/円の為替変動リスクをヘッジする動きも出ています。例えば、中国現地子会社との取引では円・人民元の直接取引を行い、為替コストを下げつつ為替予約で元安リスクに備えるケースもあります。日本と中国間では円と人民元の直接為替取引市場も拡大しています。総じて、米国取引はドル/円リスク、中国取引はドル/円と元/円リスクの両面があり、為替相場の構造や通貨管理の違いを踏まえたリスク対策が必要です。
地政学的リスクと為替変動の関係
米中対立をはじめとする地政学的リスクの高まりは、為替相場にも大きな影響を及ぼします。ただし、その影響の現れ方は一様ではなく、市場の状況によって異なります。一般に、国際的な緊張や紛争などリスクイベント発生時には、投資家が安全な資産を求める傾向があります。伝統的に日本円は「安全通貨」とみなされてきたため、世界的な経済不安や金融危機の際にはリスク回避の動きで円が買われ、急激な円高が起こることがありました。例えば、リーマンショックや欧州債務危機、あるいは北朝鮮ミサイル発射や中東の地政学リスクが高まった局面で、円が買われてドル安・円高が進行したことがあります。これは、日本の低金利や経常黒字体質、円の流動性などから「有事の円買い」という現象が起きるためです。
しかし近年、その構図に変化も見られます。地政学リスクが高まっても必ずしも円高になるとは限らず、状況によっては円安方向に振れるケースも出ています。実際、ウクライナ情勢が緊迫化した2022年には、エネルギー価格高騰による日本の貿易赤字拡大や日米金利差の影響も重なり、地政学リスクが高まっているにもかかわらず円は売られ、一時主要通貨中最弱水準にまで低下しました。一方で、同じリスク環境下でスイス・フランなど他の安全資産とされる通貨が買われる動きが目立つ場面もありました。このことから、「有事=円高」という構図が以前より崩れつつあるとの指摘もあります。
企業にとって重要なのは、地政学リスクが為替に波及する経路の多様性を理解することです。国際情勢の変化は投資家心理に影響を与え、急激な円高や円安を引き起こす可能性があります。米中対立が先鋭化すれば、中国経済減速→資金流出で人民元安、そしてリスクオフで相対的にドル高・円高、という複合的な動きも考えられます。一方、対立に伴う制裁合戦やサプライチェーン分断は、特定国への依存度が高い企業にコスト増をもたらし、それがマーケットで円売り材料と見なされる可能性もあります。中立的な立場で見れば、地政学リスクそのものが円高要因か円安要因かは一概に決まらず、その時々の市場のリスク選好度合いや関連する経済要因次第です。したがって輸出企業は、米中関係の動向や各国の外交・安全保障政策にもアンテナを高く張りつつ、自社の為替リスクにどう波及し得るかシナリオを検討しておくことが重要です。安全保障上のイベント(紛争、制裁、大規模テロ等)が起きた際の円相場の動き方が変化してきている今、過去のパターンにとらわれず柔軟に備える姿勢が求められます。
大手企業向け:為替リスク対策の王道と高度な手法
中小企業向け:実行可能な為替リスク対策
為替変動や地政学リスクを乗り切った企業事例(大手・中小企業)
為替対策を社内で実行・浸透させる方法(経営層と財務担当の連携)
上記4点については、以下資料をダウンロードしてお読みいただけます。
【輸出企業向け】為替リスク完全対策ガイド:利益を支える円安・円高対応策
\簡単30秒で今すぐ無料ダウンロード/
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!