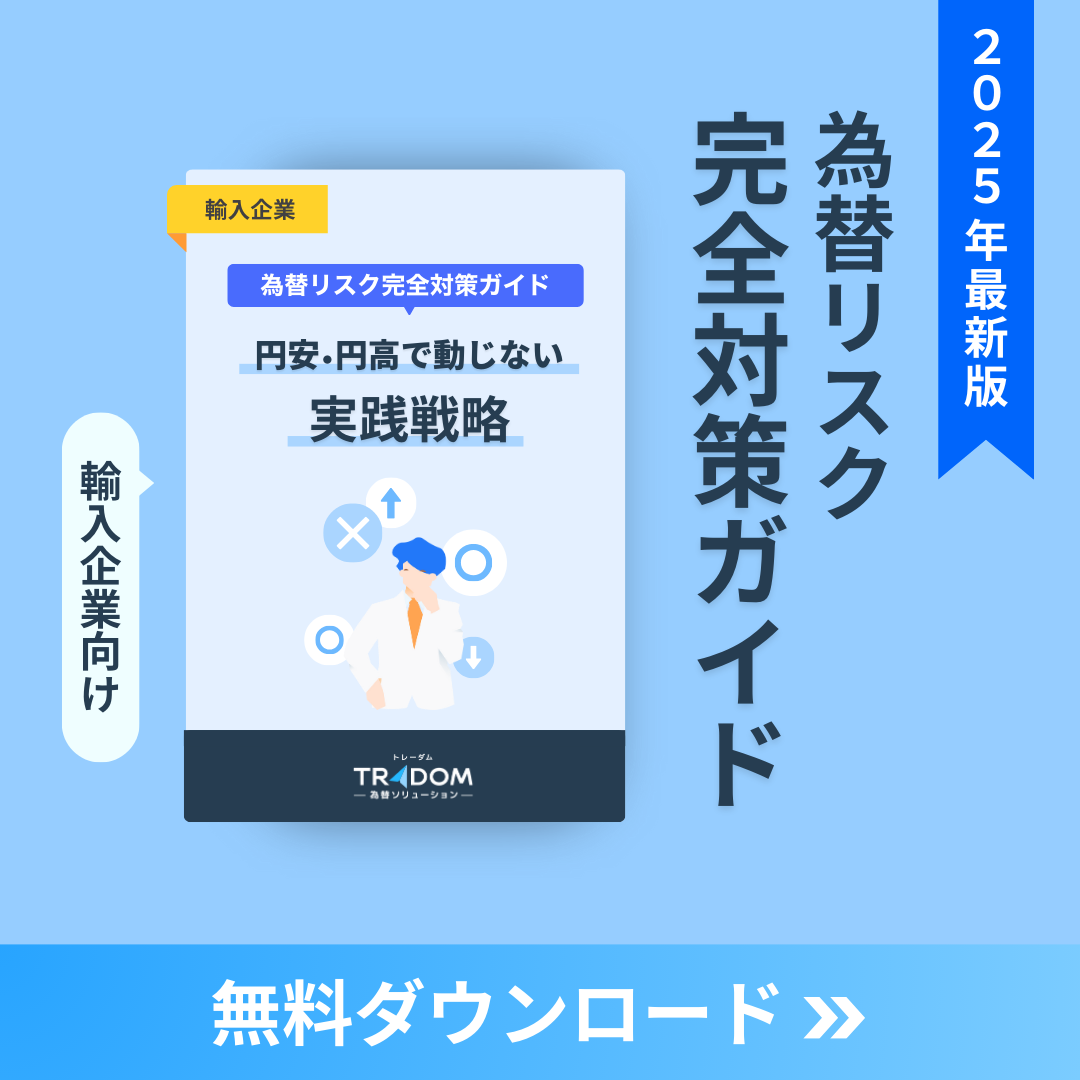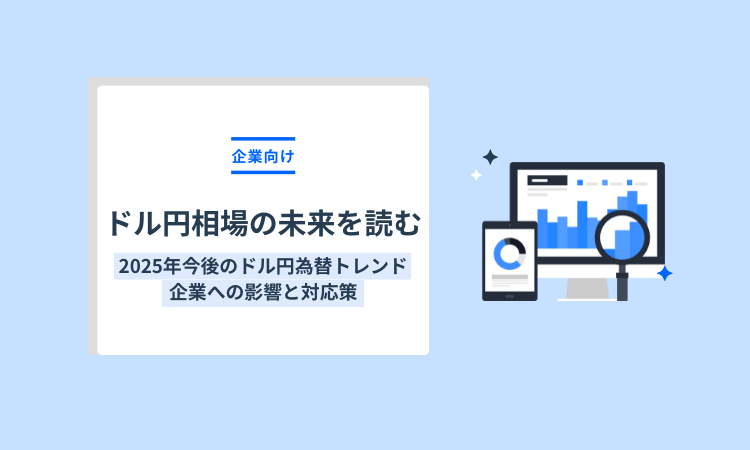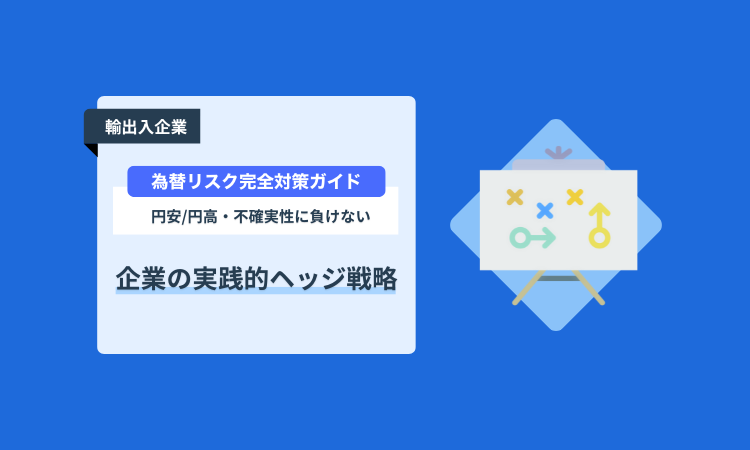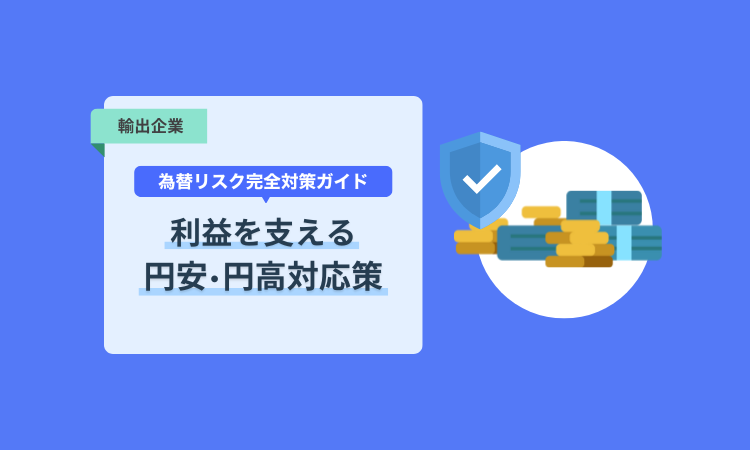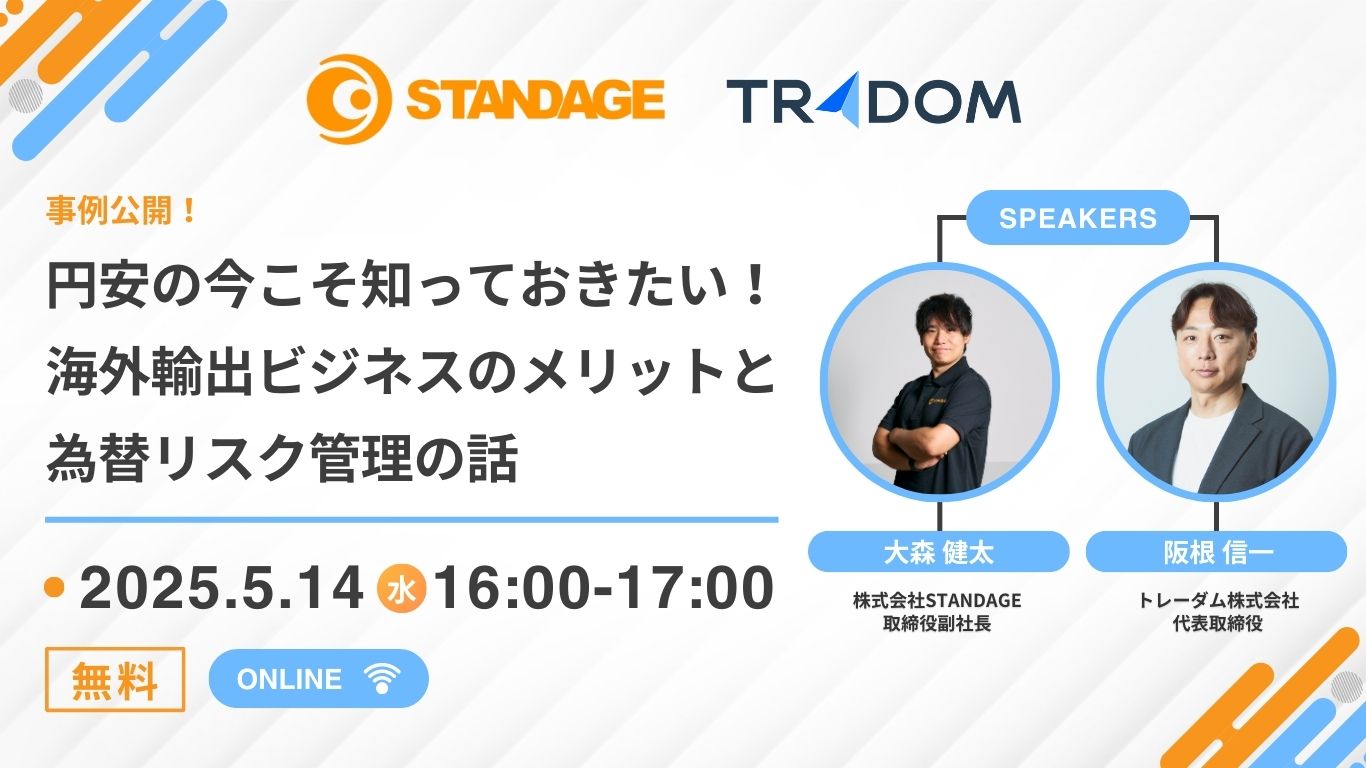為替リスクの基本
為替リスクとは、外国為替レートの変動によって生じる損失のリスクを指します。輸出入など海外取引のある企業では、円とドルなど通貨の相場変動により売上や仕入れコストが日々変動し、放置すれば利益が大きく変動してしまいます。現在のような変動相場制では為替レートは市場の需給で常に変動するため、企業にとって無視できないリスクとなっています。特に海外から原材料や製品を調達する輸入企業にとって、円安(円の価値下落)は仕入れ価格の上昇を招き利益を圧迫します。一方で円高(円の価値上昇)は同じ円貨でより多くの商品を輸入できるためコスト削減につながり、輸入企業に有利に働きます。つまり円安・円高の変動によって輸入コストは増減し、経営に直接影響を及ぼすのです。為替リスクを適切に管理すれば、こうした変動による悪影響を抑え安定した収益と競争力を維持できます。逆に対策を怠れば、相場次第で利益が吹き飛ぶ恐れがあるため注意が必要です。
為替リスクの実際の影響と事例
日米金利差の拡大、日本の貿易収支構造の大きな変化(貿易収支の赤字化)に伴い、大きく円安が進む局面が続いています。たとえば2016年から2021年頃までは1ドル=100〜115円前後と安定した推移でしたが、2022年に入ると急激な円安が進行し、一時は1ドル=150円超という約32年ぶりの円安水準に達しました。この急激な円安は日本企業に大きな影響を与え、特に輸入企業の多くが打撃を受けました。輸入品の円建て価格が1年で30%以上も高騰し、通常営業利益率10%程度の企業では一気に赤字転落しかねない水準だったのです。実際、燃料費や物流費の高騰も重なり仕入れ価格上昇分を販売価格に十分転嫁できない企業が続出しました。2022年9月時点で企業の仕入れ価格を示す企業物価指数が前年比+9.7%上昇する一方、消費者物価指数は+3.0%の上昇に留まり、仕入れコスト増を販売価格に転嫁しきれず企業側が負担を抱えている実態が浮き彫りとなりました。また、東京商工リサーチの調査によれば、円安を直接の要因とする倒産は2022年に累計17件発生し、過去5年で最多を記録しています。特に輸入品取扱いの多い卸売業や農林水産品を扱う企業で倒産が相次いだことが報告されています。
ドル円の推移
具体的な企業の事例では、商品の約9割を海外生産し輸入するビジネスモデルの企業が、円安による原価上昇が直撃しました。2022年3〜11月期決算では純利益が前年同期比12%減となり、四半期開示以来初めて2年連続の減益に陥りました。対ドルで1円の円安が生じると年間で約20億円もの営業利益減少要因になるといい、為替変動が収益に与える影響の大きさがわかります。このように、為替リスクは大企業であっても経営を左右し得る重大な課題です。一方で円高局面では、例えば原油や穀物など輸入原材料の調達コストが下がるため企業のコスト削減につながり経営を下支えします。実際、過去には急激な円高で輸入価格が下落し恩恵を受けた企業もあります。しかし為替相場は常に変動するため、円高時のメリットに安心しきっていると、ひとたび円安に転じた際に大きな痛手を被る恐れがあります。円安・円高いずれの極端な変動にも動じない企業体質を作るには、平時からの備えが欠かせません。
為替リスク対策の基本戦略
成功企業の事例紹介
4つの実践ポイント
上記3点については、以下資料をダウンロードしてお読みいただけます。
【輸入企業向け】為替リスク完全対策ガイド:円安・円高で動じない実践戦略
\簡単30秒で今すぐ無料ダウンロード/
ようこそ、トレーダムコミュニティへ!